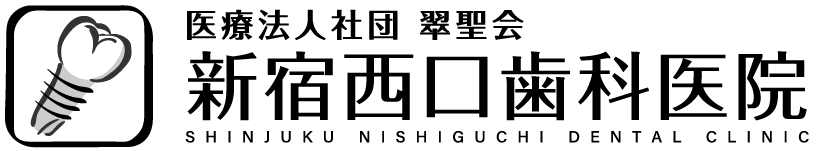歯周外科(フラップ手術)
 歯周病から歯を守るために、外科治療が必要になる場合があります。歯周病は日本人が歯を失う最大の原因といわれ、40歳以上の約8割に何らかの兆候があるとされています。
歯周病から歯を守るために、外科治療が必要になる場合があります。歯周病は日本人が歯を失う最大の原因といわれ、40歳以上の約8割に何らかの兆候があるとされています。初期段階ではスケーリングやSRP(歯石除去・ルートプレーニング)などの保存的治療で改善が期待できますが、進行して歯周ポケットが深くなると、通常の器具では歯石や細菌が取りきれないことがあります。
その際に選択肢となるのが「歯周外科(フラップ手術)」です。
歯ぐきを丁寧に開いて、直視下で歯根面の歯石・感染組織を取り除き、炎症を抑えることで歯の保存を目指す治療です。
「抜歯と言われたけれど歯を残したい」という方も、一度ご相談ください。
歯周外科(フラップ手術)とは?
歯周病によって深くなった歯周ポケット内部の歯石・細菌・炎症組織を、肉眼またはマイクロスコープで確認しながら徹底的に除去する外科処置です。
通常のクリーニングでは届かない部分にアプローチできるため、進行した歯周病の改善に効果的です。
目的は歯周組織の炎症を除去し、歯を守ることです。
このような方に適しています
- 歯周ポケットが5mm以上ある
- SRP後も炎症や出血が改善しない
- 歯がグラグラする、噛みにくい
- レントゲンで骨吸収を指摘された
- 「抜歯」と診断されたが温存したい
- 口臭が強く、歯周病と診断されている
※精密検査の上、適応を判断します。
当院の歯周外科治療の特徴
① 歯周病治療に精通した歯科医師が担当
歯周病学に基づき、外科処置の必要性・適応・予後を丁寧に診断します。無理な外科治療は行いません。
② CT・レントゲン・ポケット検査による正確な診断
骨の状態、欠損形態、歯根の形状、炎症の広がりを立体的に解析。適切な治療計画を立案します。
③ マイクロスコープや拡大視野での精密処置
肉眼では見えない歯根面の凹凸や歯石を確実に除去し、再発リスクを低減します。
④ 必要に応じて再生療法と組み合わせ可能
骨欠損の形態によっては、リグロス・エムドゲインなどの再生療法を併用し、歯の保存をより強化します。
⑤ 術後のメインテナンスまで一貫管理
外科処置後の経過観察・クリーニング・生活指導を徹底し、長期的な安定を図ります。
フラップ手術の流れ
- カウンセリング・口腔内診査
- レントゲン・CT・歯周組織検査
- スケーリング・SRP(初期治療)
- 再評価・外科治療の必要性を判断
- 局所麻酔下で歯ぐきを開き、歯根・骨面を露出
- 歯石・感染組織・炎症性肉芽の除去
- 歯根面の平滑化(デブライドメント)
- 縫合・術後管理・定期メインテナンス
治療期間の目安
・初期治療:1〜2ヶ月
・外科処置:1回(部位により複数回)
・治癒・組織安定:1〜3ヶ月
・メインテナンス:継続
※症例により異なります。
フラップ手術のメリット
- 深いポケット内部の歯石・細菌を徹底除去できる
- 炎症が改善し、出血・腫れ・口臭が軽減
- 歯の動揺度が改善することがある
- 歯を抜かずに保存できる可能性が高まる
- 再生療法との併用で予後改善が期待できる
リスク・注意点
- 術後に痛み・腫れ・出血を伴う場合があります
- 歯ぐきが下がり、歯が長く見えることがあります
- すべての歯が保存できるわけではありません
- 喫煙は治癒・成功率を大きく低下させます
- メインテナンスを怠ると再発する可能性があります
治療内容・選択肢・予後について事前に十分ご説明します。
よくある質問(Q&A)
Q. 痛みはありますか?
局所麻酔を使用するため、処置中の痛みはほとんどありません。術後は痛み止めを処方します。
Q. 必ず手術が必要ですか?
いいえ。初期治療で改善する場合は行いません。必要性を精密検査で判断します。
Q. 抜歯を避けられますか?
歯周外科は歯を保存するための選択肢であり、抜歯回避の可能性が高くなります。
Q. 仕事を休む必要はありますか?
多くの場合は日常生活や仕事への影響は軽度です。担当医が説明します。
Q. どのくらい持ちますか?
術後のメインテナンスが非常に重要です。継続することで長期安定が期待できます。
新宿で歯周外科(フラップ手術)をご検討の方へ
「歯周病が治らない」「歯を残したい」「抜歯を避けたい」
そのようなお悩みをお持ちの方は、一度ご相談ください。
当院は外科治療を前提にするのではなく、保存的治療を十分に行った上で本当に必要な場合のみ、歯周外科をご提案します。
患者さまの将来の健康を見据えた、丁寧な歯周病治療を大切にしています。
◎カウンセリング・セカンドオピニオンも受付中です。