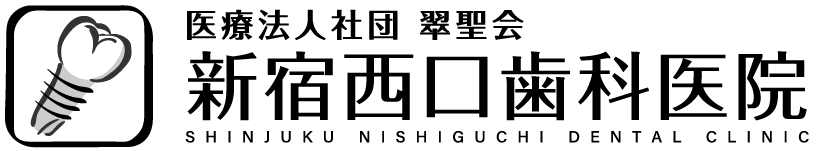歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)
 「根管治療しても治らない」方へ。根端切除術は、根管治療を行っても改善しない根尖病変(根の先の膿・炎症)を治すための外科的治療です。
「根管治療しても治らない」方へ。根端切除術は、根管治療を行っても改善しない根尖病変(根の先の膿・炎症)を治すための外科的治療です。マイクロスコープやCTで診断し、歯根の先端部分の感染組織を外科的に取り除き、歯を保存することを目的とします。
「繰り返す腫れ」「治療しても治らない痛み」「レントゲンで黒い影が消えない」方は、抜歯の前に検討すべき重要な選択肢です。
当院では、低侵襲技術と精密器具を用いて、可能な限り歯を残すための治療を行っています。
歯根端切除術が必要となる代表的な症状
歯の根の先端(歯根端)に生じた根尖病巣(こんせんびょうそう)が、従来の根管治療(歯の神経の管を清掃・消毒する治療)を何度行っても治癒しない、または再発を繰り返す場合に、歯根端切除術が必要となります。これは、歯の保存を目的とした外科的な治療法です。代表的な症状としては、歯肉の腫れや痛みが慢性的に続く場合や、レントゲン写真で根の先に大きな膿の袋(嚢胞)が確認される場合が挙げられます。また、すでに根管治療が施された歯で、根の先に器具や異物が詰まっているために薬が届かず、感染源を除去できないケースも適用となります。この手術は、抜歯を回避し、歯を残すための最終手段として位置づけられます。
- 根管治療を繰り返しても腫れ・痛みが改善しない
- 根尖病変の影(黒い影)が広がっている
- 原因不明の痛みが続く
- フィステル(歯ぐきのニキビのような膿の出口)ができている
- 噛むと痛む、浮いた感じがある
- 金属や大きな土台で再治療が困難
なぜ歯根端切除術が必要になるのか?(原因)
歯根端切除術が必要になる主な原因は、歯の根の先に残存する細菌感染、すなわち根尖病巣(こんせんびょうそう)が、従来の根管治療では除去しきれないことにあります。従来の根管治療(歯の神経が入っていた管を清掃・消毒する治療)で病巣が治癒しない、または再発を繰り返す背景には、主に以下の要因があります。
1. 根管の複雑な形態
- 根管の湾曲や分岐: 歯の根管はまっすぐな一本の管ではなく、複雑に湾曲していたり、細い枝のように分岐(側枝や副根管)していたりすることがあります。
- 不完全な清掃: この複雑な構造の奥深くに潜んでいる細菌や感染物質を、通常の器具や薬液だけでは完全に除去しきれず、感染源が残ってしまうことがあります。
2. 根尖部の問題
- 根尖部の封鎖不良: 以前の根管治療で詰めた材料(根管充填材)が、根の先端(根尖)でしっかりと封鎖できておらず、細菌が再び侵入して感染を起こしてしまうことがあります。
- アピカルデルタ: 根の先端(アペックス)付近で根管が網目状に細かく分かれている部分(アピカルデルタ)があり、ここに細菌が残りやすいことがあります。
3. 異物や石灰化の存在
- 根管内の異物: 以前の根管治療時に使用したファイル(清掃器具)の破片などが根管内に残ってしまい、その先の感染源に薬液が届かなくなってしまうケースです。
- 根管の石灰化: 加齢や刺激によって根管の一部が石灰化し、根管が非常に細くなったり閉鎖したりして、感染部位までのアクセスが遮断されてしまうことがあります。
当院で行う精密診査
- 問診(治療歴・症状の経過)
- デンタルX線による病変の確認
- 歯科用CTで根尖の状態を立体的に診断
- マイクロスコープでの破折・穿孔の確認
- 噛み合わせと補綴の評価
レントゲンだけでは判断できないため、CT診断は必須です。
歯根端切除術の治療方法
① 局所麻酔後、歯ぐきの切開
歯ぐきを最小限に切開し、炎症部位へ直接アプローチします。
② 骨の一部を取り除き、根尖へアクセス
必要最小限の骨削除により、根の先端に到達します。
③ 感染した根尖と肉芽組織を除去
歯根の先端3mm程度を切除し、周囲の感染組織を徹底的に除去します。
④ 逆根管充填(逆根充)
根尖側からMTAなどの高い封鎖性を持つ材料を充填し、再感染を防ぎます。
⑤ 縫合(1〜2週間で抜糸)
小さな傷で済むため、治癒も比較的早く進みます。
歯根端切除術の成功率
マイクロスコープ・MTAなどの最新技術を用いた歯根端切除術は、成功率約80〜90%と報告されています。
(European Journal of Endodontics 等の文献より)
治療後に期待できる改善
- 腫れや痛みの再発が止まる
- 根尖病変が徐々に縮小 → 骨が再生
- フィステルの消失
- 噛む痛みの改善
- 抜歯を回避できる可能性が高まる
歯根端切除術の適応外となる場合
- 歯根破折がある場合
- 広範囲に骨吸収が広がっている場合
- 根が極端に短い場合
- 歯周病の進行が著しい場合
- 保存しても予後不良が確実と予測される場合
その場合は、インプラント・ブリッジなどの機能回復治療をご提案します。
治療後の注意事項(予後管理)
- 術後数日は腫れや痛みが出ることがあります
- 運動・飲酒・入浴は当日控えてください
- 歯ぎしり・食いしばりがある場合はナイトガードが有効
- 定期検診で根尖部の治癒を確認します
費用について
歯根端切除術は主に自由診療となり、用いる材料(MTAなど)や歯の部位により費用が異なります。
事前に明確に説明し、同意のうえで治療を進めます。
リスク・副作用
- 術後の腫れ・痛み・内出血
- 傷口の感染
- 治癒が遅れることがある
- 症状が改善しない場合、抜歯となる可能性がある
よくある質問(Q&A)
Q. 再根管治療とどちらが良いですか?
どちらが適しているかは原因次第です。
再根管治療が難しい場合に、歯根端切除術を選択します。
Q. 手術は痛いですか?
局所麻酔を行うため痛みはほとんどありません。術後の痛みも数日で落ち着きます。
Q. 仕事は休む必要がありますか?
ほとんどの方は翌日から通常通り生活可能です。
Q. 再発することはありますか?
再発の可能性はゼロではありませんが、精密処置とMTA充填によりリスクは大きく減少します。
抜歯を避けたい方へ ― まずはご相談ください
歯根端切除術は抜歯の前に検討すべき、歯を守る最後の選択肢の一つです。「治療したのに治らない」「症状が繰り返す」方は、早期の精密診査が重要です。
新宿で根の病気や根尖病変でお悩みの方は、新宿西口歯科医院へお気軽にご相談ください。