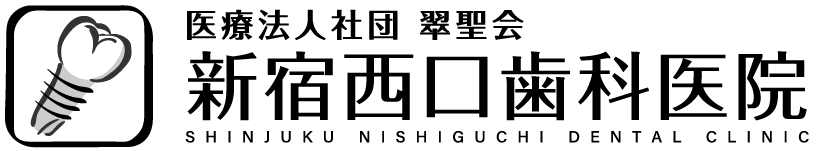歯髄保存治療(神経を残す治療)
 「神経を残すこと」は、歯の寿命を守る最良の選択です。むし歯が深く進行した場合、「神経を取る(抜髄)」という従来の選択肢が一般的でした。
「神経を残すこと」は、歯の寿命を守る最良の選択です。むし歯が深く進行した場合、「神経を取る(抜髄)」という従来の選択肢が一般的でした。しかし歯髄(神経・血管)は、痛みを感じるだけの組織ではなく、歯へ栄養を届け、防御機能を持ち、細菌感染に対する免疫的役割を担う非常に重要な器官です。
歯髄を失うと歯は脆くなり、将来的に破折や根管治療、抜歯へ進むリスクが高まります。
だからこそ当院では、できる限り歯髄を保存し、天然歯を長く使い続けることを最優先に考えています。
「神経を残せる可能性があるのに抜髄されてしまう」ケースを減らしたい——その想いで日々診療を行っています。
歯髄保存治療とは?
むし歯が神経に近い、または到達している可能性がある場合でも、適切な診断・処置により歯髄を残すことを目指す治療です。従来であれば抜髄が選択されていた症例でも、マイクロスコープ・精密除去・生体親和性の高い材料を用いることで、歯髄の生活反応を維持できる可能性が高まっています。
なぜ歯髄を残す必要があるのか?
- 歯の強度(破折防止)を保てる
- 歯の再石灰化や免疫機能が働く
- 根管治療・再治療リスクが減る
- 将来の抜歯・インプラントを回避できる可能性が高まる
- 治療回数・費用・全身負担が軽減できる
このような方に適しています
- むし歯が深いと言われた
- 「神経を取るしかない」と診断されたが残したい
- 冷たい物・甘い物でしみるが持続痛はない
- 根管治療を避けたい
- 歯を長く残したい
※適応には精密診断が必要です。
当院の歯髄保存治療の特徴
① マイクロスコープ精密治療
最大約20倍の拡大視野で虫歯を選択的に除去し、健全歯質と歯髄へのダメージを最小限に抑えます。
② MI(ミニマルインターベンション)に基づく切削量最小化
削る量が少ないほど歯髄を守れるため、必要最小限の処置を徹底します。
③ 高生体親和性材料(MTAセメント・バイオセラミック)使用
封鎖性が高く、抗菌・歯髄保護・象牙質形成を促す最新材料を使用します。
④ 正確な診断とリスク評価
症状、生活歯髄反応、レントゲン、CT、歯髄温存の可能性を科学的根拠に基づき判断します。
⑤ 術後経過観察と長期フォロー
治療後の痛み・感染・象牙質形成を定期的に確認し、予後を管理します。
主な歯髄保存治療の種類
① 間接覆髄法(Indirect pulp capping)
感染の危険性がある深在性う蝕でも、すべてを削らず、一部を残して封鎖することで歯髄を保護します。
歯を大きく削らないためMI治療と非常に相性の良い方法です。
② 直接覆髄法(Direct pulp capping)
ごく一部の露髄(小さな神経露出)に対して、MTAなどを用いて歯髄を保護・封鎖します。
③ 生活歯髄温存療法(Selective caries removal)
マイクロスコープ下で感染象牙質を慎重に除去し、生活歯髄を残す最新概念です。
④ 部分断髄法(Partial pulpotomy)
露髄部の数ミリのみを切除し、健康な歯髄を残す方法。外傷や急性症例にも有効な場合があります。
治療の流れ
- 問診・痛みの種類・既往歴の確認
- レントゲン・CT・生活歯髄検査
- マイクロスコープによる精密診断
- 必要最小限のう蝕除去
- MTA・生体材料での封鎖
- レジンまたは補綴物による最終修復
- 術後経過観察(1〜6ヶ月)
歯髄保存が可能なケース・難しいケース
保存が期待できるケース
- 自発痛がない
- 痛みが短時間で消える
- 感染が根尖周囲に及んでいない
- 破折がない
困難なケース
- 強い自発痛・夜間痛がある
- 根尖病変が大きい
- 歯が大きく割れている
- 重度の歯周病を伴う
※診断結果により根管治療を提案する場合があります。
治療期間の目安
1〜2回の治療で終了することもありますが、経過観察を含めると1〜6ヶ月となることがあります。
リスク・副作用
- 術後に冷痛・咬合痛が出る場合があります
- 感染が進行した場合、根管治療へ移行する可能性があります
- 歯髄保存の成功が100%保証されるものではありません
よくある質問(Q&A)
Q. 他院で「神経を取るべき」と言われました。本当に残せますか?
残せるかどうかは精密検査で判断できます。セカンドオピニオンも承ります。
Q. 痛みはありますか?
麻酔を使用するため、治療中の痛みはほとんどありません。
Q. どれくらい持ちますか?
状態・生活習慣・咬合管理・経過観察により長期安定が期待できます。
Q. 小児でも受けられますか?
部分断髄法など、年齢や状態に応じた保存療法が行える場合があります。
新宿で歯髄保存治療をご検討の方へ
歯の神経は一度失うと元に戻りません。
だからこそ「残せる可能性がある段階で適切に対応すること」が重要です。
当院は、むやみに抜髄を行うのではなく、患者さまの将来の歯の健康を見据え、科学的根拠に基づいた最適な選択肢をご提案します。
「歯を長く残したい」「神経を守りたい」方は、ぜひ一度ご相談ください。
◎初診相談・セカンドオピニオンも受付中です。